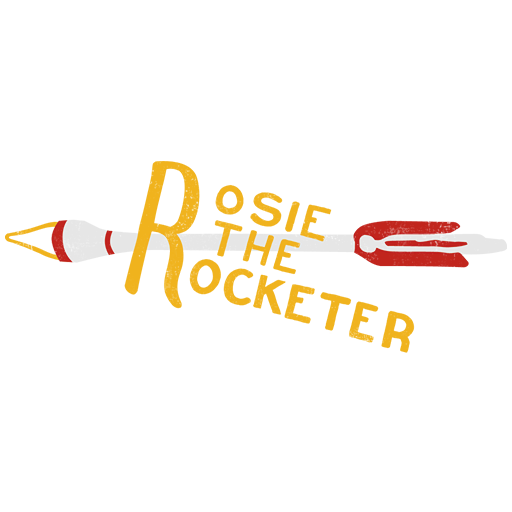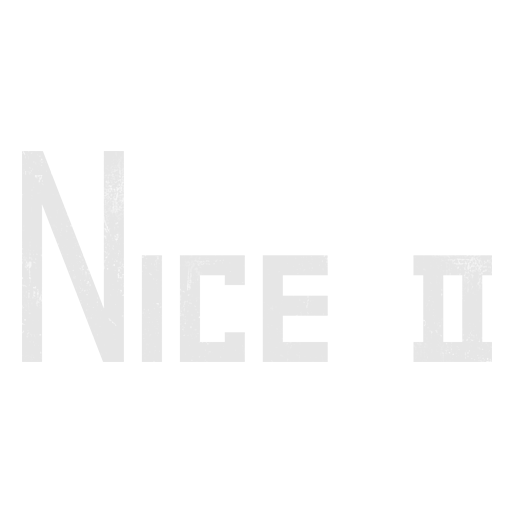どうも、皆さん!今月も恒例の歴史的碑文とマークをお届けします。今回は「ロージー・ザ・ロケッター」を追加するため、ラインナップを少し調整しました。通常は各国家やツリーに均等に順番が回ってくるよう、同一国家のデカールを連続して追加することはありませんが、今回は「歴史の1ページ」イベントと合わせて追加する絶好の機会でした。ロケット弾やロージー愛好家の皆さん、ぜひコレクションに加えて楽しんでいただければ幸いです!もちろん、今回追加された他のマークも気に入っていただければ嬉しいです。ぜひご覧ください!
| |
9月8日(月)20:00(JST) から 10月8日(水)18:00(JST)まで、下記のデカールを獲得可能です。
各タスクは、ランクIII以上の兵器を使用することで達成できます。
|
新デカール
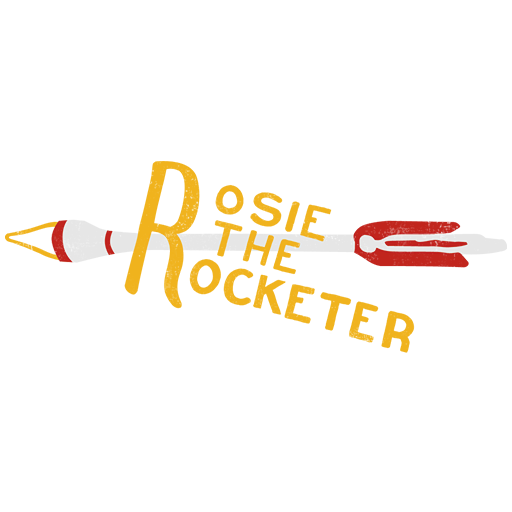
アメリカ 「ロージー・ザ・ロケッター」マーク
|
| 
カナダ 第419飛行隊「もう一つどうぞ(Have Another)」マーク
|
アメリカの航空機で、地上または海上目標をロケット弾を使用して30回撃破する
|
| イギリスの航空機で、爆弾を使用して敵プレイヤーを20回撃破する
|
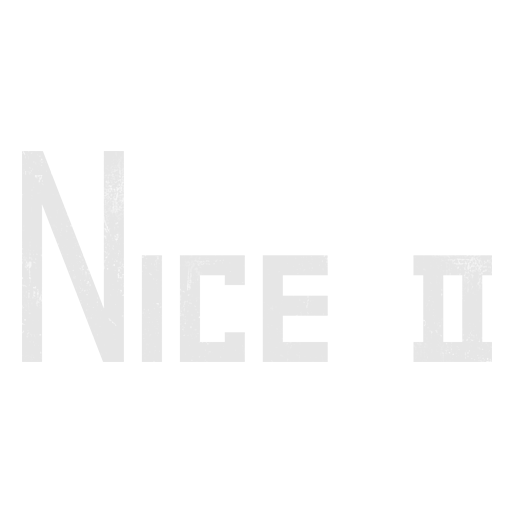
フランス 碑文「ニース II(Nice II)」
|
| 
イスラエル 第254飛行隊の記章
|
| 
日本 海軍協会の記章
|
フランスの地上車両を使用して15,000スコアを獲得する |
| イスラエルの航空機で、ミサイルを使用して敵プレイヤーを20回撃破する |
| 日本の艦艇を使用して20,000 スコアを獲得する |
「ロージー・ザ・ロケッター」マーク
アメリカ陸軍チャールズ・カーペンターのパーソナルマーク。第二次世界大戦中、歴史教師を経て偵察パイロットとなったカーペンター少佐は、パイパー L-4 グラスホッパーに搭乗していました。兵装もなく、戦果も限定的だったことに不満を抱いた彼は、機体にバズーカ砲を数基取り付け、火力を強化するための申請を提出しました。脆弱な機体とロケット弾の制限された射程にもかかわらず、チャールズはドイツ軍の装甲車両6両(うち2両はティーガーI戦車)を撃破した功績を認められ、瞬く間に伝説的な人物になりました。彼は自機を「ロージー・ザ・ロケッター」と命名しました。これは第二次大戦中、アメリカ工場労働力の大半を占めた女性たちを象徴する「ロージー・ザ・リベッター」をもじったものです。やや粗雑なデザインのロケット弾とそれに伴う碑文は、航空機の右側、コックピットの真下に塗装されていました。
第419飛行隊「もう一つどうぞ(Have Another)」マーク
カナダ空軍 第419飛行隊「もう一つどうぞ(Have Another)」マーク。どの航空機にこのマーキングが施されたかについては資料によって矛盾しているものの、第419飛行隊に所属したイギリスの尾部銃手兼造形作家であったベネット・レイ・ケニオンの作品であることは疑いようがありません。彼の作品は後に映画『大脱走』のインスピレーション源となりました。撃墜され・捕虜となった後、彼は小包用紙の切れ端に脱走準備を記録し、これらの断片が数十年後、映画の情景に明確なインスピレーションを与えました。詳細は不明ですが、このマークはおそらくオーストラリア人の搭乗員から着想を得たもので、イギリス連邦の象徴としてふさわしい例だと言えます。つまりこれは、オーストラリアをテーマにした記章が、イギリス人によってデザインされ、カナダ空軍飛行隊の航空機に塗装されたのです。このマークは、爆弾の上に立つ漫画風のカンガルーと、その袋の中で双眼鏡を使用して目標を探す子カンガルーが描かれています。このマークは、飛行隊のハリファックス爆撃機のうちの1機の右側、コックピットの下部に塗装されていました。
碑文「ニースII(Nice II)」
フランス陸軍 第2胸甲騎兵連隊「ニースII」の碑文。英語では一見異なる意味に見えてしまいがちですが、この刻印はフランスの沿岸都市ニース(英語発音は「ニース」)を指します。第二次世界大戦中および戦後、車両に都市名を付けることはフランス軍で一般的な慣行であり、名称は乗員の出身地、部隊の編成地、または配備地域に基づいて選ばれることが多くありました。数字の「II」は、戦場で破壊または退役した最初の「ニース」戦車が存在したことを示しています。「ニースII」は1950年代にフランス軍が使用した、戦後のM4A1シャーマン戦車(登録番号802594)です。車体側面、砲塔下部にこの碑文が塗装されていました。
第254飛行隊の記章
イスラエル空軍 第254「ミッドランド」飛行隊の記章。1980年に編成され、当初はクフィルC.10を運用しており、後にC.2型およびミラージュ IIICJを採用し、1982年のレバノン戦争では警戒任務に従事しました。同飛行隊は、保有していたクフィルC.2がアメリカ海軍へ移管される予定であったため、1984年に解散しました。その後、アメリカ海軍VF-43部隊の「アグレッサー」プログラムに編入され、F-21A ライオンと再指定されました。このマークは海岸線を背景に様式化された鳥を描き、赤い輪郭線は航空機の窓からの眺めを表している可能性があります。このマークは全機に施されたわけではありませんが、一般的に飛行隊の航空機の尾翼上部に配置されていました。
海軍協会の記章
日本海軍協会の記章。大日本帝国海軍の直轄組織ではありませんでしたが、海軍活動への国民的支持を築くため1917年に設立されました。当初は海軍拡張、特に国家的な支援を必要とする大型軍艦の建造推進に重点を置いていました。第二次世界大戦中は、海軍の兵員募集や軍人とその家族への支援に重点が移りました。この典型的な海軍のマークは、主にバッジとして広く使用されていました。

|
| 
|
復刻デカール

中国「中央防空学校」の記章
(作成者:フォーラムモデレーターRedmisty)
|
| 
イタリア イタリア社会共和国 第10機動魚雷艇艦隊「ルポ(Lupo:狼の意)」大隊の記章
|
中国の地上車両を使用して、敵航空機を20機撃破する |
| イタリアの地上車両を使用して、60%以上の戦闘貢献率でバトルを20回プレイする |

スウェーデン 第1スカニア航空連隊(F 10)「幽霊飛行隊」の記章
|
| 
ドイツ 第559重戦車大隊の記章
|
| 
ソ連 第9親衛戦闘機連隊(9GvIAP)のアメト=ハン・スルタンのパーソナルマーク
|
スウェーデンの航空機を使用して、1~3位でゲームを3回終える |
| ドイツの駆逐戦車を使用して、敵プレイヤーを40回撃破する |
| ソ連の航空機を使用して、敵プレイヤーを50回撃破する |
「中央防空学校」の記章
中国陸軍の中央防空学校の記章。1933年に中国民用航空局によって創設され、1934年1月に杭州検橋飛行場に正式に設立されたこの学校は、その後何度か移転と名称変更を繰り返しました。そのカリキュラムは、ドイツやイギリスなど、さまざまな国から翻訳された教材に基づいており、学生たちに複数の有用な視点を提供していました。また、ドイツ、チェコスロバキア、ソ連などから砲を購入し、さまざまな外国製の対空装備も使用していました。車両は少なかったものの、少なくとも1両のヴィッカース砲兵トラクターがあり、その下部の装甲板に学校の記章が塗装されていました。
イタリア社会共和国 第10機動魚雷艇艦隊「ルポ(Lupo:狼の意)」大隊の記章
イタリア社会共和国 第10機動魚雷艇艦隊「ルポ(Lupo:狼の意)」大隊の記章。装甲部隊とは程遠い存在ながら、同大隊は1944年に数台のL6/40軽戦車を調達しました。ただしその運用経歴の詳細は不明瞭で矛盾する点が多く存在します。トリノ北部のチリエで3両が劣悪な状態で回収されました。少なくとも1両は部品のために完全に分解され、残る1両を実戦配備した可能性が高いです。1両はヴェナーリア(トリノ南部)に配備され、もう1両は後にアルバで確認されました(ただし20mm砲は装備されていませんでした)。これらが同一車両か別物かは不明ですが、カモフラージュの簡単な分析からは同一である可能性が示唆されています。最後の、あるいは唯一稼働していた戦車は、1944年末にミラノの鉄道車両基地で放棄されました。大隊の記章を基にした狼のマークは、砲塔前面に塗装されていました。
第1スカニア航空連隊(F 10)「幽霊飛行隊」の記章
スウェーデン空軍 第1スカニア飛行隊(1. Skånska Flygflottiljen)F 10の記章。その起源は1942年まで遡り、当時同飛行隊はグラディエーターおよびJ20戦闘機を運用していました。任務が早朝や深夜に実施されることが多かったため、地元住民は航空機の音は聞こえても姿を見ることは稀であったため、この部隊は非公式に「幽霊飛行隊」の異名を得ました(公式コールサインはヨハン・レッド(Johan Röd)のままでした)。この記章は2002年の連隊解散まで断続的に使用され、J35 ドラケンやJ37 ビゲンの尾翼に塗装されていました。最も有名な使用例はビゲン 57号機で、鮮やかな赤色に塗装され、尾翼に幽霊が顕著に描かれ、国家ラウンデルに取って代わって使用されていました。前輪左側のハブには極小の秘密の幽霊が確認できます。伝えられた内容からは、同機がルレオのF 21を訪問した際、誰かがホッケーのステッカーをその車輪に貼り、F 10に戻った際には幽霊で覆い隠されていたと言う話です。
第559重戦車大隊の記章
ドイツ国防軍 第559重戦車大隊(Schwere Panzerjäger-Abteilung 559)の記章。1939年8月26日に編成された同大隊は、当初3.7cm対戦車砲のみを装備していましたが、武装の変化に伴い再武装と改称を数度繰り返しました。1944年4月10日、初陣のヤークトパンター配備直前に「重」の称号を付与されましたが、III号突撃砲および後にIV号戦車/70(V)の運用も継続しました。同大隊は第二次世界大戦終結まで活動し、ヘールの戦いやアルデンヌ攻勢に参加しました。このマークはヤークトパンターをやや現代風に描いたもので、戦争末期には大隊に所属するヤークトパンターの右前部泥除けに塗装されていたのが確認されています。
第9親衛戦闘機連隊(9GvIAP)のアメト=ハン・スルタンのパーソナルマーク
ソ連空軍 第9親衛戦闘機連隊(9GvIAP)のアメト=ハン・スルタンのパーソナルマーク。1940年にパイロットとして卒業したアメト=ハンは、戦闘機パイロットおよびテストパイロットとして輝かしい経歴を残しました。単独で30機、共同で19機の敵機を撃墜した戦績により、ソ連邦英雄の称号を授与されました。彼は戦争をLa-7で終えることになりますが、1943年にはクーバン上空でP-39 エアラコブラを頻繁に操縦しており、このマークはそこから由来すると言われています。蛇のマークに関する写真による証拠は現存していないようですが、この時期に彼の航空機を目撃した人たちは、彼の航空機に黄色のジグザグ模様の蛇が描かれていたと報告しています。蛇の選択は、少なくともテーマ的には、エアラコブラと関連するため辻褄は合います。信頼できる情報によると、この蛇は彼のP-39の機体の左側に描かれており、ヘビの頭はコックピットの前に、尾はエンジン排気口の端にあったとされています。
毎月のマークは、以下の手順にて確認することができます:カスタマイズ画面下部→タブ「月間デカール(Monthly Decals)」。1か月後、これらのデカールはそれぞれ該当するカテゴリーに移動されます。
| |
これらのデカールのタスクの進行状況は、プレイヤープロフィール→デカール→月間デカール(Monthly Decals)で確認することができます。ここで「進捗状況の確認(Track progress)」をクリックすると、格納庫から進行状況を確認することができます。
|
それぞれの記章には詳細な説明がついてきます。この説明には、マークの歴史、デザイン、使用した兵器、該当する場合は史実では兵器のどこに配置されていたかなどが書かれています(一部の記章はバッジからとられたものであるため、すべてが該当するわけではありません)。これにより、史実に基づいた配置をお好みで容易に再現することができます。
9月のセレクションを気に入っていただけると幸いです。次期大型アップデート「タスクフォース(Tusk Force)」が実施されるまでは、是非皆さまのコレクションにこれらを追加して楽しんでください。ご要望はいつでもお待ちしております。それではまた来月会いましょう!
The War Thunder Team